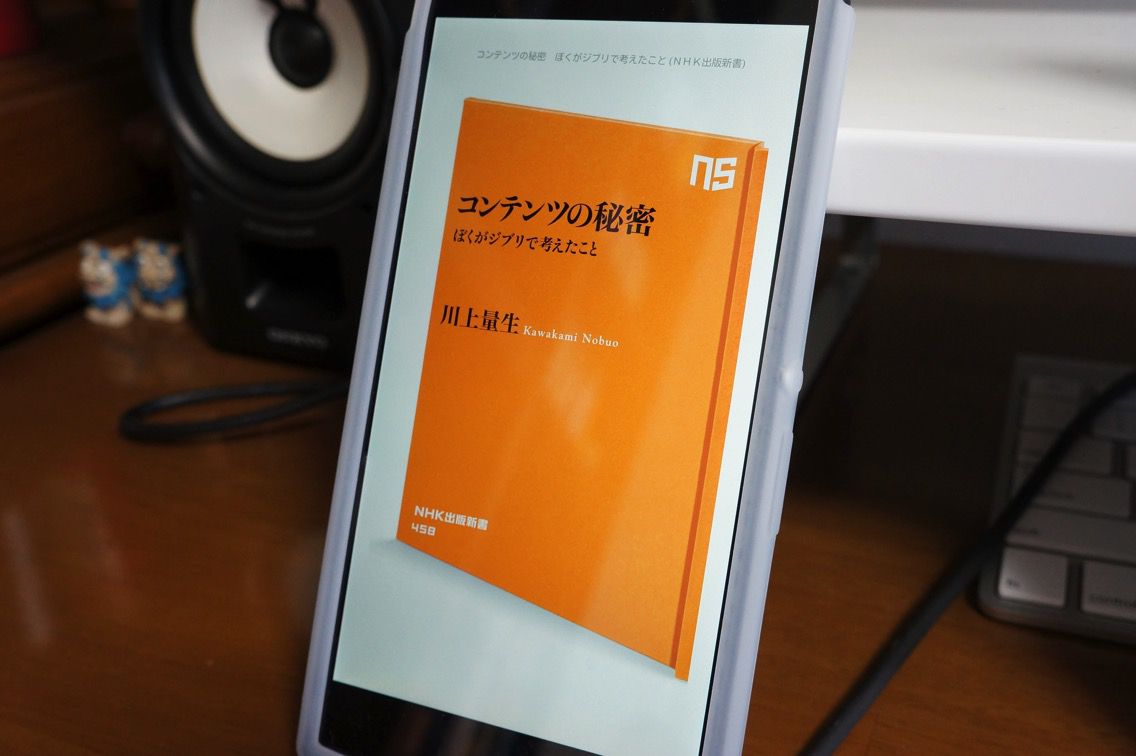
コンテンツを作ってる人はピンとくるところがありますよ。
ジブリみたいに大きなコンテンツだけじゃなくて、個人ブログをやってる僕でも勉強になるところがたくさんありました。
「主観」こそコンテンツ
「自分が情報発信をして意味があるんだろうか」と思うことって結構あります。
その問いに対して心から納得できる答えってあんまりないんですよね。でもやっとこの本を読んで納得しました。
客観的情報量と主観的情報量という言葉を使ったぼくのコンテンツの定義は、次のとおりです。
小さな客観的情報量によって大きな主観的情報量を表現したもの
現実で誰でも同じように見えてるもの(客観的情報)から、自分が強く受けとったもの(主観的情報)だけをピックアップして表現=「コンテンツ」と定義しています。
確かにこの書評についてもそう言えますね。誰でも同じ文章を読めるけど、取り上げたくなる場所は人によって違います。
それは、この本を読むまでに考えてきたことや経験してきたことが人によって違うからです。つまり、客観的な情報を前にすると、誰もが主観的な情報を作り上げます。
だから、事実を伝えるだけのメディアならともかく、そこに自分の意見が入ることで、それはもう他にはないコンテンツになります。
そう考えると、誰でも情報発信をすることの意味はあります。
でも当然、それまでの知識や経験が人によって違うものだから、面白い主観を持つ人、その逆の人が生まれてくるわけですね。人気のクリエイターと不人気のクリエイターが生まれるのが納得できます。
日々勉強と経験だなー。
頭の中の主観を誰でもわかる「ふつう」に変換
昔のブログを見てると、僕はどうも頭の中のことを文章に落としこむのが苦手なようで、気づくと「ポエム」になることが多いです。
しかも質の悪いポエムで、ぼく以外の人間には理解不可能な文章になってるんですよね。というか今読むと自分でも理解できません…。
思考を文章に変換する作業って、ただ文章にするだけではダメで、誰でも分かるように変換しなきゃいけないんで、高度なワザなんですよ。
コンテンツを見て観客がどう思うかを想像するのは、言うほど簡単ではありません。観客はクリエイターほどコンテンツに対して思い入れはないものです。
クリエイターが真剣にいままでにない新しいコンテンツをつくろうとした結果、観客が付いていけないというのはありがちなパターンです。だから、それをふつうのお客さんの目線に引き戻す役割を誰かが担わなければいけません。それはプロデューサーの重要な役割だと鈴木敏夫さんは言います。
鈴木さんは、監督からなにか相談されるたびに「ふつうはこうです」ということをよく言っています。「ふつう」をもっとも嫌いそうな監督に対して、ふつうの見方や考え方の話をするわけです。それがプロデューサーの役割だというのです。
天才すぎる人は、もう「ふつう」がわかんない。天才すぎる宮崎監督に「ふつう」を教えるために鈴木プロデューサーの存在があるんです。
自分の考えを誰が読んでも面白く(わかりやすく)表現してる人の何がスゴイかって言うと、自分でコンテンツを作りつつ、誰でも理解できる「ふつう」に変換できることがスゴイんだなぁと、この一文を読んで納得しました。
よく「難しいことを簡単に」って言われますが、そういうことなんですね。
人に見せるためにコンテンツを作る以上、頭を良く見せようとしてムズい言葉を使いまくるってのは最悪なことなんですね。
ひっかかりを作る
ただし、主観を誰にでもわかる「ふつう」に変換すると言っても、美しさは求めないほうがいいとのこと。
分かりやすい文章というのは、綺麗なパターンの組み合わせでスーッと読めてしまい印象に残らないから、ところどころ読みにくくして、〝引っかかり〟をつくらなければならないということです。
誰もがキレイだと感じる人の顔はたくさんの人間の顔を組み合わせた「平均的な」顔だそうです。
誰もキレイだと認めるけど、そこには引っかかりがない。パンチが足りないってこと。
例えば文章を書く場合、「美しさ」とか「ウマさ」は求めるべきではないってことです。主観をいかに純度を落とさずに文章に落とし込めるかが勝負なんです。
それでも僕が発信する理由
なんか世の中って「何しても自分よりすごい人がいてかなわない」って思いがちなんですよね。
いや、確かにすごい人はすごいなーって思うんだけど、そこに入り込む余地がないかというと違うんですね。
主観がある限りコンテンツは生み出す価値はあります。立場上弱そうな個人でも発信する理由をこの本から知ることが出来ました。
主観の純度を高めながら、誰にでもわかるように「コンテンツ」としてうまく成立させることができた人が「面白い」と他人に思われるんだなーと。
天才じゃない僕はもっと練習とか経験が必要になってくるんだろうけど、発信すべき理由を見つけられたので、それだけでも価値がありました。

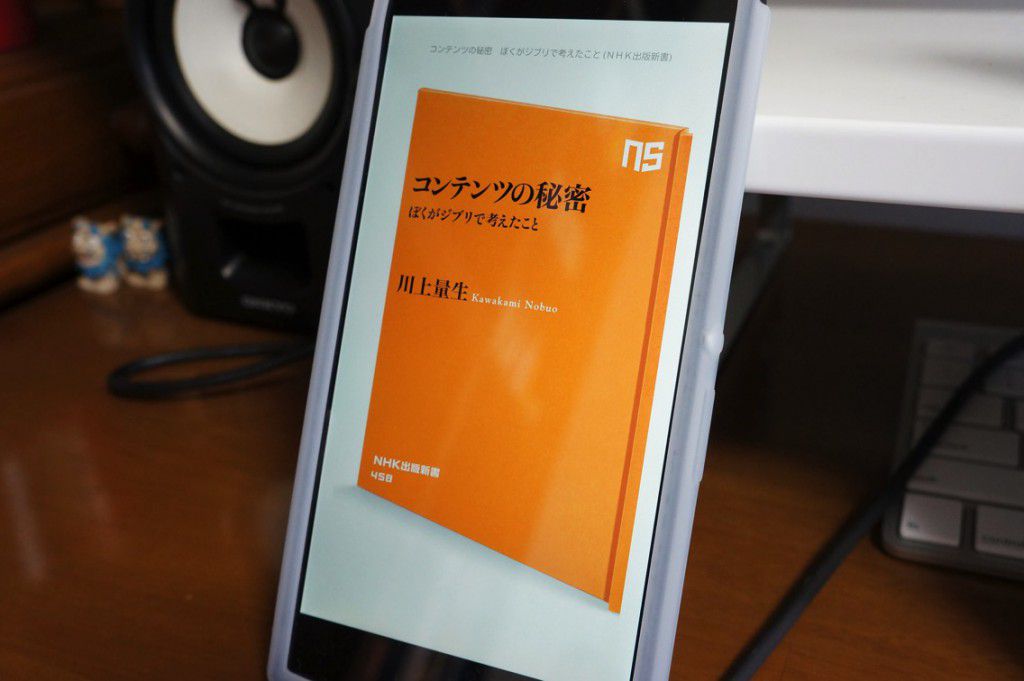


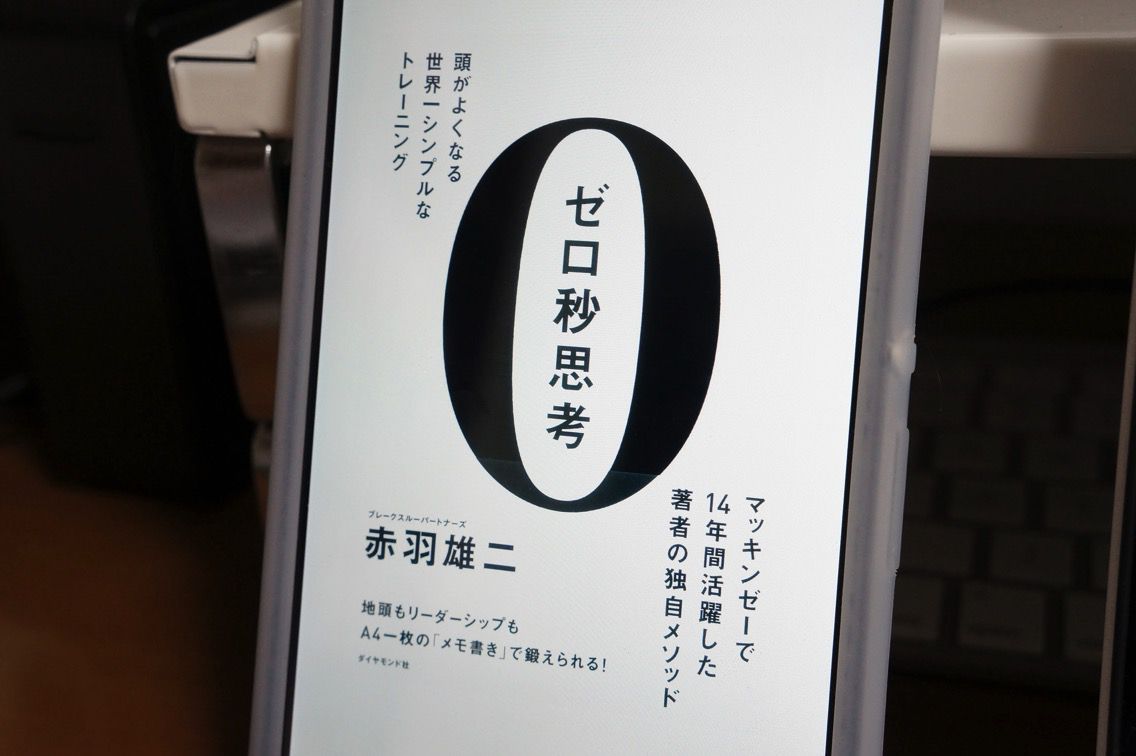
参考になりました、ありがとうございます。
記事がおもしろかったです!
ぼくも情報発信を続けていきたいと思います。